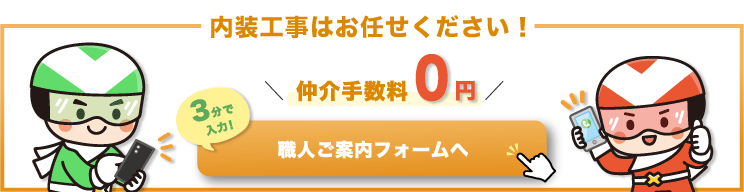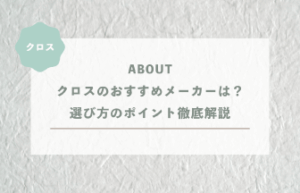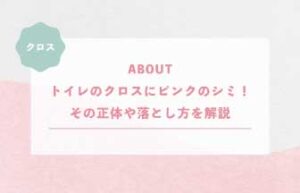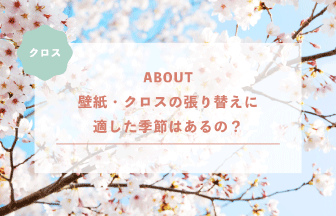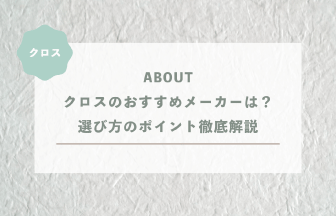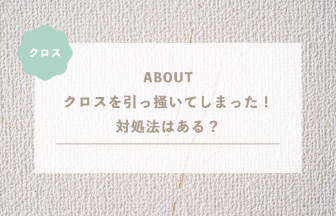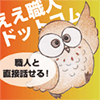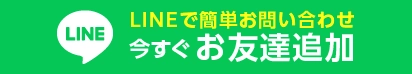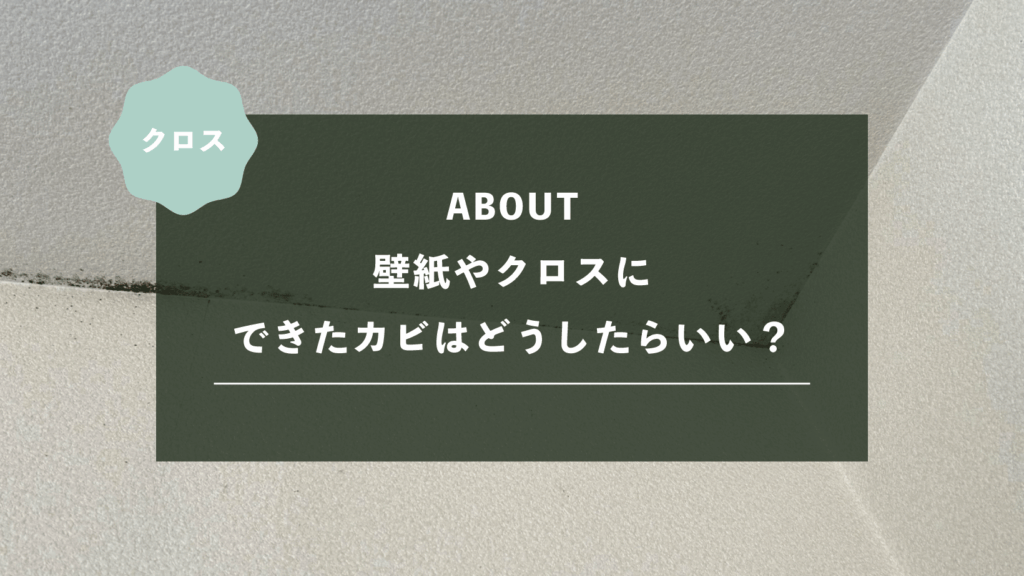
「気づいたら壁紙に黒い点々が…」
「押し入れの壁がうっすら黒ずんでいる…」
そんな経験をしたことはありませんか?
壁紙やクロスに生えるカビは、見た目の不快さだけでなく、健康被害や住まいの劣化を招く厄介な存在です。
放っておくと下地まで浸食し、大規模なリフォームが必要になることも考えられます。
本記事では、壁紙・クロスにカビが生える原因・応急処置の掃除方法・根本解決となる張り替え工事・再発を防ぐ予防策を解説します。
壁紙・クロスにカビが生える原因
カビは「湿度・温度・栄養源」の3条件がそろうと発生します。
壁紙に生えてしまう背景を理解することが、対策の第一歩です。
湿気と結露
- 室内の湿度が60%を超えると、カビが繁殖しやすくなります。
- 冬場の窓際や北側の壁は結露が起こりやすく、壁紙に水分が吸収されカビの温床になります。
換気不足
- 押し入れやクローゼットなど空気がこもる場所は、湿気が滞留しやすい環境といえます。
- 換気が十分でないとカビが発生しやすくなります。
栄養源(ホコリや糊)
- 壁紙を貼る際の糊(でんぷん質)は、カビにとって格好のエサとなります。
- また、ホコリ・皮脂汚れなどもカビの繁殖を助長します。
室温
- 20〜30℃はカビが最も活発に育つ温度帯。
- 夏の梅雨時期だけでなく、冬の暖房と結露が重なる時期も要注意です。
壁紙のカビを放置するとどうなる?
見た目が不衛生に
白い壁に黒い斑点が広がると清潔感が失われ、広がってしまうと部屋全体が暗い印象になります。
また、カビの範囲がどんどんと増えていってしまいます。
健康被害
カビの胞子は空気中に舞い、吸い込むとアレルギーや喘息、鼻炎の原因となります。
特に小さなお子様や高齢者の方は注意が必要です。
下地材の劣化
壁紙の下にある石膏ボードや木材にまでカビが侵食すると、単なる掃除では解決できません。
張り替えや補修が必須となります。
自分でできる壁紙カビの応急処置

「壁紙にポツポツと黒い点がついている」程度であれば、早い段階で応急的に掃除をすることで、カビの広がりを防ぐことが可能です。
放置するとカビが壁紙の奥まで根を張ってしまいますので、軽度のうちに対処しておきましょう。
掃除の前に準備するもの
カビ取り作業では、胞子を吸い込んだり手に付着したりしないように、必ずゴム手袋など保護具を用意してください。
- ゴム手袋
- マスク(できれば不織布マスク以上)
- ペーパータオルまたは雑巾
- 消毒用エタノール(70%前後が効果的)
- 綿棒(細かい部分の処理用)
これらを手元に揃えてから作業に取り掛かるとスムーズです。
掃除の手順
-
表面のホコリを落とす
まずは乾いたペーパータオルで壁紙表面を軽くなでるように拭きます。
強くこするとカビが潰れてシミになったり、胞子が空気中に舞って広がる原因になるので、やさしく扱うのがポイントです。 -
エタノールで除菌
カビが付着している箇所に消毒用エタノールをスプレーします。
広範囲にかけるのではなく、狙った部分にピンポイントで噴霧しましょう。
その後、ペーパータオルで「押さえるように」水分を吸い取ります。綿棒を使えば、細かい隙間やクロスの凹凸部分もきれいに処理できます。 -
仕上げの乾拭き
最後に乾いた布で軽く拭き上げ、余分なエタノールを取り除きます。
液体が残ると壁紙の変色やシミの原因になることがあるため、必ず仕上げの乾拭きを忘れないようにしましょう。
掃除の際の注意点
- 漂白剤は使わない
一般的な塩素系漂白剤は強力ですが、壁紙の色落ちや変色を引き起こしやすく、かえって見た目が悪化してしまいます。
家庭での応急処置には不向きです。 - 範囲が広い場合は無理をしない
数センチ程度であれば上記の方法で対応できますが、壁一面に広がっている、何度も同じ場所に再発する、といったケースは内部までカビが根を張っている可能性が高いです。
その場合は自己処理で完璧に落とすのは難しいため、専門の内装業者やリフォーム業者に相談するのが安心です。
防カビクロスの活用
クロスには機能性を備えた商品が存在します。
もし張り替えを行うのであれば、下記のようなクロスを使用しておくのも対策の一つです。
- 防カビ加工クロス:カビの発生を抑制する成分が含まれている
- 通気性クロス:湿気をこもりにくくし、結露の多い場所に最適
日本の国産メーカーで機能性に優れた商品を取り扱っているメーカーは多く存在します。
下記記事では、主要国産メーカーをご紹介していますのでよろしければご覧ください。
壁紙のカビを防ぐ予防策
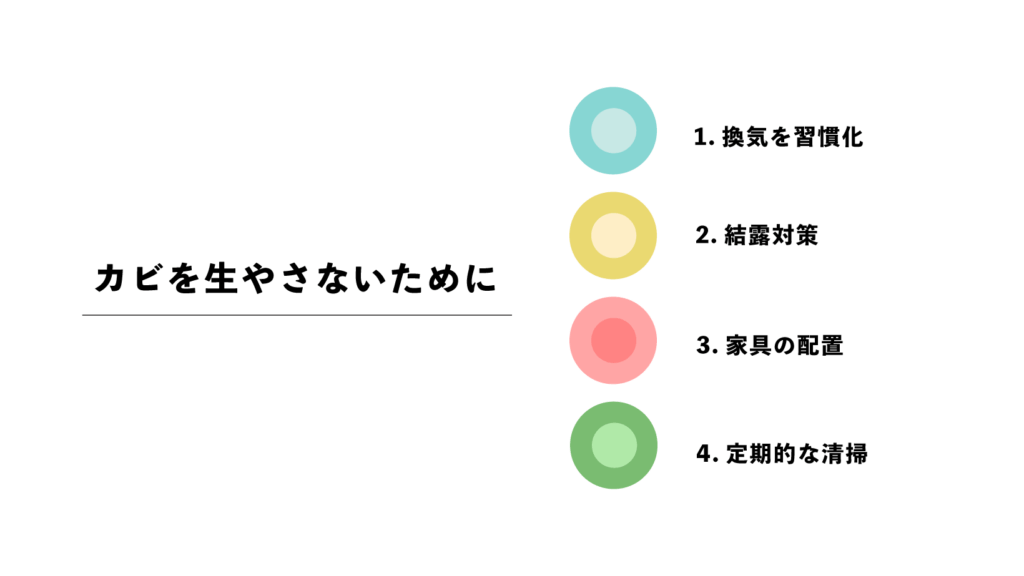
そもそも論になりますが、普段からカビを「生やさない」工夫が何よりも大切です。
特に日本の夏場は高温多湿になり、カビにとっては都合の良い環境になりやすいので注意が必要です。
1. 換気を習慣化する
カビが繁殖する大きな要因は湿気です。
室内に湿った空気がこもらないように、こまめな換気を心がけましょう。
- 1日2〜3回は窓を開ける
晴れている日や風が通る日は、数分でも良いので窓を開けて空気を入れ替えることが効果的です。 - 換気扇やサーキュレーターを活用
窓が少ない部屋やマンションの北側の部屋では、自然換気が難しい場合もあります。
その際は換気扇やサーキュレーターを使って空気の流れを強制的につくると、湿気がたまりにくくなります。
2. 結露を防ぐ工夫
冬場や梅雨時期は、窓や壁に水滴がつきやすく、それがカビの温床になります。
結露を防いでおくことは、壁紙を長持ちさせるうえでも重要です。
- 窓に断熱シートを貼る
窓の内側に断熱シートを貼ることで、外気との温度差を和らげ、結露を軽減できます。 - 二重サッシや内窓の設置
予算に余裕があれば、二重サッシや内窓を導入すると断熱効果が高まり、結露対策としても非常に有効です。 - 除湿機やエアコンの除湿運転を活用
湿度が60%を超えるとカビが活発に繁殖しやすくなります。
除湿機やエアコンのドライ運転を組み合わせて、湿度を40〜60%までに保つよう意識しましょう。
3. 家具の配置で通気性を確保
家具を壁にぴったりとつけてしまうと、空気が滞り、湿気がこもってカビが生えやすい環境になってしまいます。
- 壁から5〜10cmほど離して設置
わずかな隙間でも空気の流れが確保され、湿気がこもりにくくなります。 - 特に注意すべき家具
タンスやソファ、ベッドなど、大きな家具ほど通気性が失われがちです。
設置の際には余裕を持たせるようにしましょう。
4. 定期的な清掃とメンテナンス
ホコリはカビの栄養源となるため、こまめに掃除をすることも予防につながります。
- 壁や窓際を軽く拭き取る
月に1〜2回でも、壁紙や窓枠を乾いた布で拭くだけでカビの発生率は下がります。 - 押し入れやクローゼットも忘れずに換気
収納スペースは空気がこもりやすく、カビの温床になりがちです。
晴れた日には扉を開けて風を通す習慣をつけましょう。 - エアコンや換気扇のフィルター掃除
ホコリや汚れがたまると換気効率が落ち、結果的に湿気がこもりやすくなります。
季節の変わり目には必ずチェックしてください。
これってカビなの…?
トイレや洗面所など、水回りにピンク色のシミができていたことはありませんか?
一見カビのように思ってしまいますが、これは「ロドトルラ」という酵母菌の一種なんです。
詳しくは下記の記事で解説していますので、ピンク汚れに悩んでおられる方はぜひご覧ください。
まとめ
以上、壁紙・クロスのカビが生える原因・応急処置の掃除方法・根本解決となる張り替え工事・再発を防ぐ予防策を解説しました。
壁紙やクロスに発生してしまったカビは、応急処置・張り替え・予防策で対応可能です。
日頃からの予防を意識し、極力湿気が溜まらないような工夫を心がけましょう。
また、もし発生してしまっても、初期段階であれば自分で掃除をして取り除くことは可能です。
しかし、壁一面に広がっていたり石膏ボードまで繁殖してしまっているのであれば、健康リスクの観点からも業者に依頼することをおすすめします。
「はりかえ隊」では、カビてしまったクロスの張り替えに対応できる専門業者を多数ご紹介しています。
地域に合った信頼できる職人を見つけて、カビのない安心・快適な住まいを取り戻しましょう。